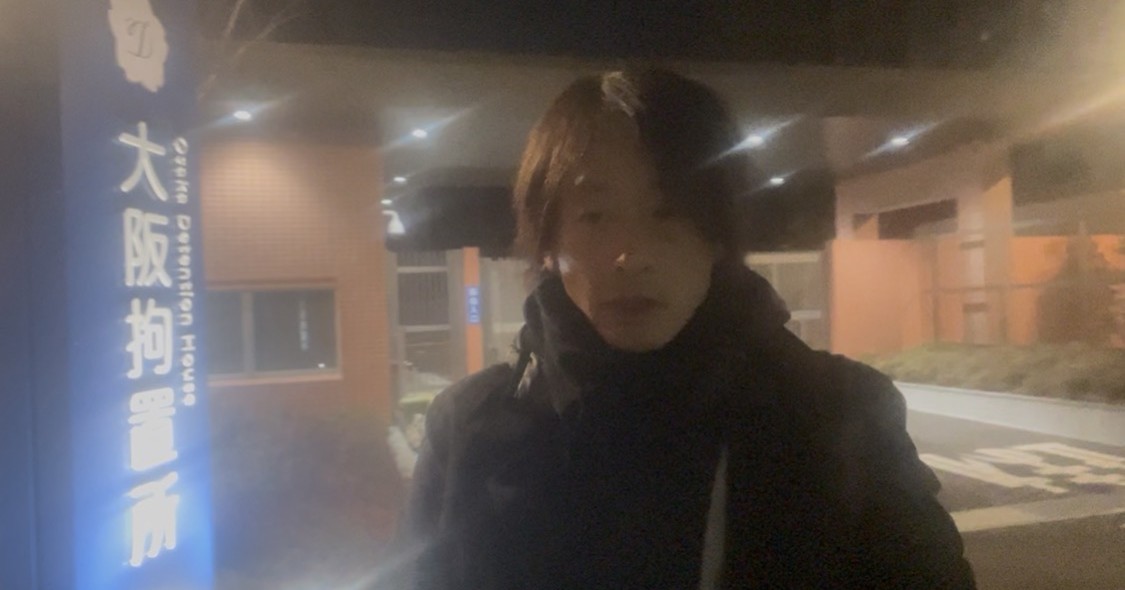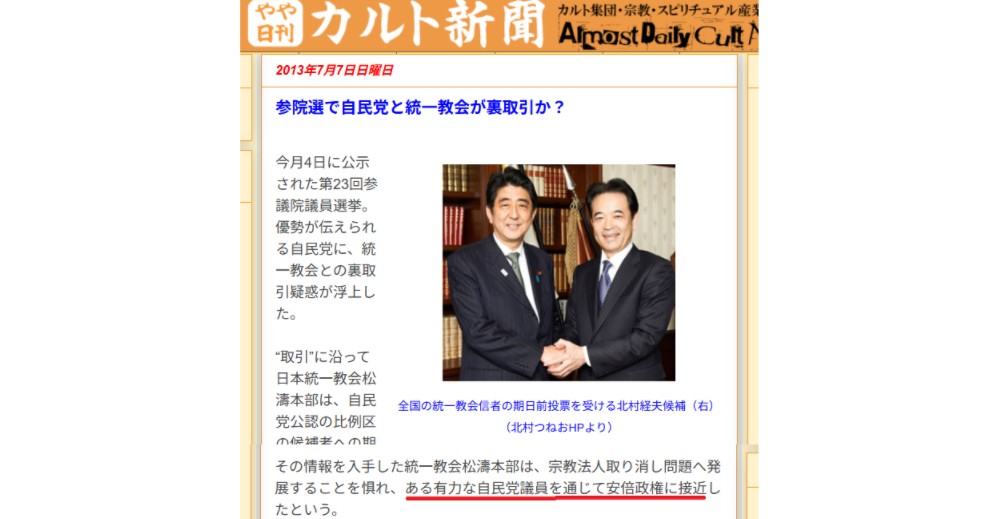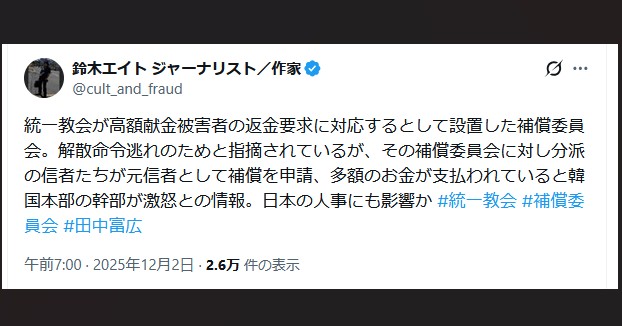「一から十までデタラメ」「もう研究者生命は終わり」国内初のHPVワクチン副反応大規模調査を行った疫学研究者が指摘する相手
(当初、サポートメンバーに先行配信していた記事です。読者登録で全文読めます)
子宮頸がんなどHPV(ヒトパピローマウイルス)による様々ながんの罹患を予防するワクチンとして知られるHPVワクチン。将来の子宮頸がんワクチン罹患を防ぐ目的で、10代女児への接種が行われてきた。

鈴木貞夫教授(名古屋市立大学)
現在も小学6年生から高校1年の女子が定期接種の対象年齢ととなっており、厚労省によって積極的勧奨がなされている。一方、同ワクチンによって深刻な副反応被害を受けたとして集団訴訟も起こっている。対象年齢の子どもを持つ保護者にとって気がかりなのは副反応への懸念であろう。
だが、同ワクチンの安全性については10年前に国内で実施された大規模な疫学調査によって担保されている。
一方、HPVワクチンによる薬害を主張する原告サイドは、この疫学調査の結果について否定的な見解を示している。
HPVワクチン/子宮頸がんワクチンの副反応をめぐる疫学調査「名古屋スタディ」を行ったのが、日本における疫学研究の専門家である鈴木貞夫教授(名古屋市立大学)だ。これまで何度か同裁判を傍聴しているという鈴木教授にインタビュー取材を行った。
取材日は2月15日、zoomで話を伺った。時系列で言うと、2月10日に東京地裁で被告側申請専門家証人の中村好一名誉教授への主尋問が行われた期日の後になる。
インタビュー取材に先立つメールのやり取りで、事前に鈴木教授からいただいたのは以下の内容だ。
「名古屋市から依頼されたHPVワクチンの疫学研究に『名古屋スタディ』と命名し、出版したことで薬害裁判の当事者になりました。すでに意見書は提出してあります。この研究は,名古屋市からの請負いですので、こちらが主体的に研究結果を曲げる理由や動機はありませんし、もし、そんなことをしたのであれば、公職を追放されても仕方がないと思っています。それを向こうにあてはめれば分かるとおり、八重・椿両氏は専門知識を使用して間違ったことをしているということで、論文は撤回、社会的制裁が必要というのが私の考えです」
ぜひ鈴木教授にインタビュー取材をしたいと申し込んだ。鈴木教授は、被告側申請の専門家証人として証言した角田郁生氏と「立場は同じ」として取材を受諾。「むしろ問題を多くの人が知るようになった方が良いっていうことが私の個人的な考え」と立場を明確にした。
――2月10日の東京地裁でのHPVワクチン訴訟にも傍聴に来ておられました。傍聴した感想を聞かせてください。
「中村先生はすごくうまくお話をされました。私が証人として立つ可能性もあったわけですが、中村先生が立たれたということは、私以外にも私と同じ考えの人がいるということなんですよね。だけど向こうは、私の感想ですけど、結局椿先生が立つしかなかったと。ああいう考え方をしている人はおそらく他にいない。それをどう言うかは別問題として、肌感覚的にはそうです。‶研究者生命を脅かすような〟と中村先生がおっしゃった通り、あれは一般的な言葉で言うと‶デタラメ〟です。私はずっとそれを‶比較妥当性がない〟という言葉で言っていたんですけど。比較妥当性がない研究をしたら、結論はデタラメですという話なんだけど、デタラメというのを科学者が言うってことに関してはいろいろな障害があるので、講演会でクローズドの時には‶それを翻訳するとデタラメという意味です〟というくらいは言いますけど…。」
――そこは裁判で中村先生がはっきりおっしゃったということは、かなり強いということですよね。
「はい。僕たちは全体的に科学のフィールドの話しかしないので。中村先生が今回良かったのは科学プラス、先生が今まで培ってきたエキスパートとしての距離感や肌感覚、あるいは価値観といったそういったものを言っていただいて。最後に青木先生が出てきたくだりも本当に素晴らしいと思いましたね」
――鈴木先生の師匠に当たる方ですよね。
「あれは面と向かって一回言われたこともあるんですよ。嬉しくて、やってよかったなという気がしたのですが、中村先生に非常に高く評価していただいているということで、ありがたいと思っています」
――名古屋スタディに関してですが、この裁判の焦点、中心的なところに置かれて審理、議論されていくと思うのですが、鈴木先生の論文、名古屋スタディに関する調査が2016年で発表が2018年という理解でよろしいでしょうか?
「調査は2015年ですね。2015年の9月から10月ぐらいまでデータを集めて、12月に速報を一回出しているんですよ。‶12月の速報に間に合うように〟ということで、かなり急いでやった。で、その速報が向こうからの圧力で潰されたという経緯です。訴訟が2016年だから、15年度から16年度に変わった段階で大きくガラッと変わって、私は本当にやりにくかった。2016年に訴訟が起きたから、いろんな意味で名古屋スタディに圧力がかかった。あまり私は表だって言っていないけど、論文を書くことに対しては最初の約束がありますよね。私が論文書くという約束で引き受けているので。だからどんなに状況が悪くなっても〝書いても大丈夫ですか?〟という訊き方は一回もしてないです。そういうことを言って〝やめてください〟と言われるのが嫌だから。だからずっと出して、論文が落ち続けて、私たちはすごく大事なことだと思ってたから、いい雑誌から投稿しているんだけど、出版社から見たら当たり前の結果なんですよ、これは。だからもう有名雑誌とかことごとく落ちて…。論文掲載が遅いのは、若干、心が折れ気味だったので、それくらい時間がかかった。2015年から2018年頭だから、もう丸々2年以上掛かっているんですよ。そういう経緯です」
――このHPVワクチン訴訟の裁判自体への思い、この訴訟が起こされていること自体への受け止めについて。
「私はこのワクチンについて、全く知識のない状況で引き受けたわけです。最初から立場があれば私のところに依頼は来なかったと思いますよ。私が立候補したんじゃなくて、名古屋市が私のことを選んだわけです。研究をやってみたら、データを見る前にどのくらいの結果が出るかなという期待というか予想はあったのですが、それよりもうんと低い、〝何の関連もない〟というのがポンと出てきてしまったと。皆、関連があると思っていて、そのうえで実際データを取って解析しました、でも関連は出ませんでした。だから、因果関係がない上で、裁判を起こして、たとえ勝ったとしても因果関係が元々ないわけだから治療法なんてできませんよね。だから、そういう点で、間違ったものをどんどん進めていって、裁判に勝ったとしても、お金以外で何も得るものはないと。だから治療もできないし、治癒もない、時間だけが経っていく。皆さんおっしゃってるのは〝間違ったものに対して、どんどん時間だけが経っていって、体調不良が治らなくなっていく〟〝あるべき治療があったはずなのに、それが受けられないということで、誰も幸福にならない〟私たちの立場からすると、間違ったものの上に正しい方策はないし、健康や幸福もない、そういう理解でいます」
――原告の人たちの話を聞くなり、発信している内容を見ると、鈴木先生の論文に対して、いろいろと設楽・森川論文や八重・椿論文、隈本邦彦氏の「名古屋スタディという研究は存在しない」というような論説などが出ていて、それが正しいものだっていうことを前提に発信をされていて、〝自分たちの方が科学的にも正しいんだ〟というところが、かなり信念的に持ってしまっているところがあって。そこを突き崩すっていうのって、私も報道に関わる人間でありながら、科学や医学にそんなに詳しくないという立場からすると、なかなかそこの判断というのは、〝科学的にこれが正しいんですよ〟ということをいくら言っても、〝いや、こういう説もありますよ〟となかなか理解してもらえないというジレンマを私から見ても思うのですが、そういう点を、鈴木先生が見られて、どう突き崩していけばいいのかというところについて。
「私たち研究者は実はこういうことには慣れてなくて、だいたい科学的に正しい事しか見聞きしないので。これは、明らかに間違っているものに対する方策というものは、教科書的にどう動くというのが何もないんですよね。だから例えば私たちの研究仲間でも〝鈴木さん、こんなもう箸にも棒にも掛からないもの、放っておきなさい〟と言う人はかなりいます。だけど、私は〝間違ったものはすべて潰す〟という方針でいっております。今、対立論点はこれだけ(資料にあげられた8つの対立)だと思うんですよ。だから八重・椿論文は撤回請求のレターを出しました。ただ、これはJJNS(八重・椿論文を掲載した日本看護科学学会の英文誌)が〝撤回しません〟という結論を出したので、JJNSとしては終わった問題だと思ってます。あとはいろいろ論説が出てるのですが、論説が出るごとに‶あなたが言っていることは間違っている〟という反論を書いてます。出版されているのが鈴木論説1と2。裁判でもちょっと出てきた設楽・森川論文には非常に初歩的なミスがあります。(資料に)鈴木論説3と書いてあるけど、今これ査読中です」