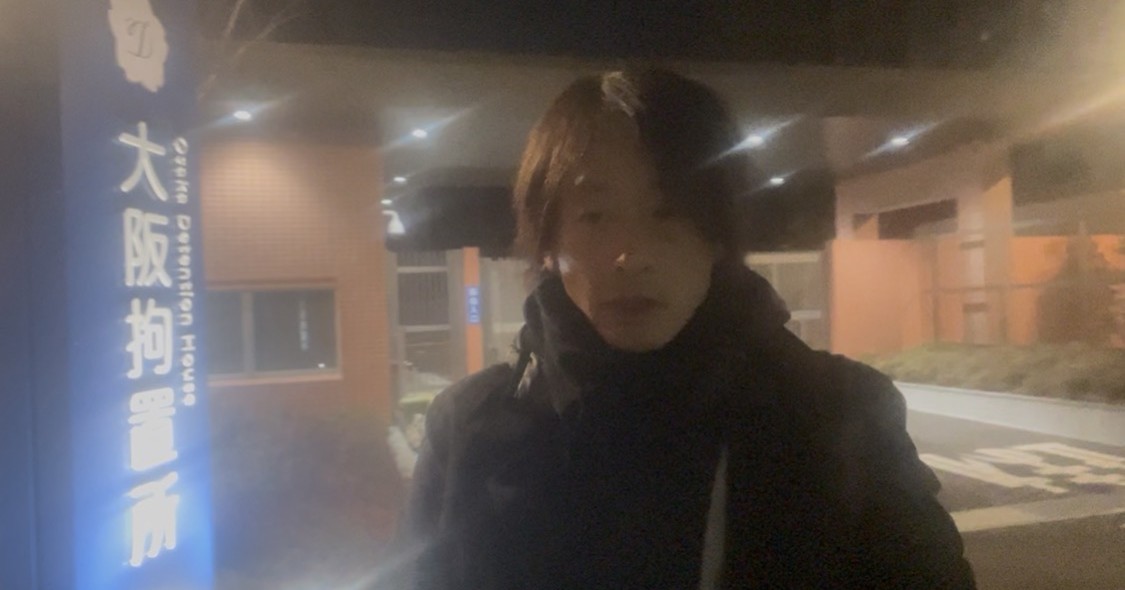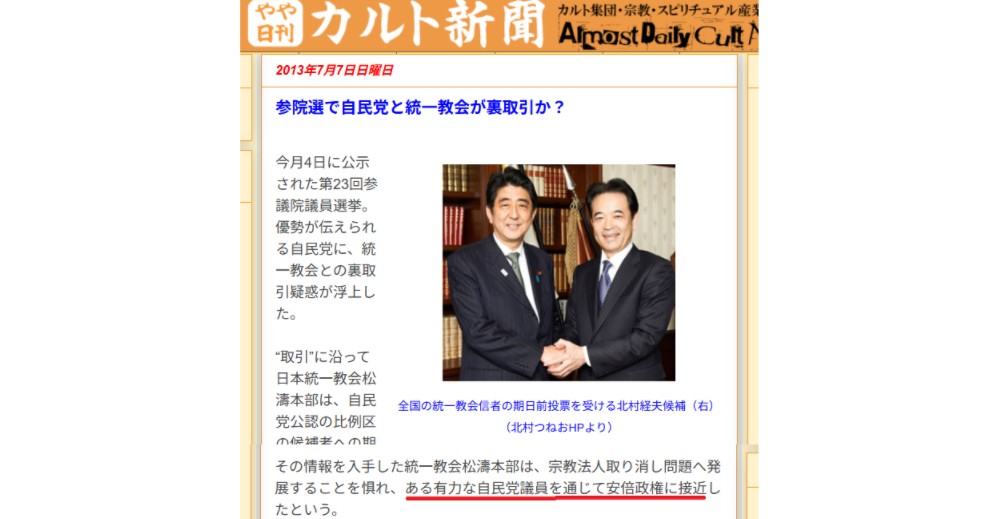統一教会サイドからのSLAPP訴訟で鈴木エイトを完全勝訴に導いた山田健太教授の意見書を全文公開
SLAPP訴訟の概要(一審)
当該訴訟は筆者のこれまでの報道や出演番組での発言、統一教会系集会での発言、X(旧Twitter)での投稿内容について名誉を毀損されたとして統一教会から業務委託を受け報酬を得ている団体の代表者(教団信者)が1,100万円の損害賠償を求め2023年10月3日に提訴したものだ。提訴会見の質疑応答で原告訴訟代理人は文科大臣による解散命令請求を牽制する意図があり提訴を急いだとの旨を答えている。後日、統一教会系のシンポジウムにおいても訴訟の目的を「鈴木エイトからメディアの仕事を取り上げること」と発言しており、私の言論封殺を目論んだSLAPP訴訟であることは明白だ。
訴因は以下の5つだが、総合して私が原告を「嘘つきでペテン師」と論評したとする珍妙な論を展開していた。
①2013年に「やや日刊カルト新聞」に寄稿した記事の内容
『“後藤ケース”は、脱会説得に応じず、逆に“氏族メシア”として家族を説き伏せるためにマンションに留まり、居直った末に果てにニート化してただの“引きこもり”となった男性信者が、役柄を“転換”し“拉致監禁に耐えきった英雄”として統一教会内でスターダムにのし上がったというだけの話だ。実際のところ、後藤氏は引っ込みが付かなくなっているのではないか。記憶の改変が起こる土壌は全て整っている』
②2015年に「やや日刊カルト新聞」に寄稿した記事の写真のキャプション
『信者内では有名な後藤徹氏も本紙主筆が声を掛けると手を挙げて応答。12年間に及ぶ引きこもり生活の末、裁判で2000万円をGETした後藤徹・拉致監禁強制改宗被害者の会会長』
③2022年8月に読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」に出演した際のコメント
『そうですね。裁判の過程でも、統一教会側が信者を大量動員して、もう傍聴席を埋め尽くしたっていうことがありました。そういうなんか異様な熱気に裁判所が流されたって点もありまして、この原告自体も、もうほぼ引きこもり状態の中、いつでも出ていけるような状態、自分より体格の劣るような母親と2人きりの時であっても全く出ていかなかったこともあって、外形的にはほぼ引きこもり状態なのではないかと思われるんですが、そういう訳でちょっとまあ全体的になんか変な感じの流れの裁判だったなと思いますね』
④2023年7月に統一教会現役2世信者によるシンポジウムを取材した際に、登壇者である福田ますみ氏から逆質問を受けた際の返答
『どうでもいいです。ご自由に受け取ってください。はい、以上です』
⑤2023年8月にX(旧Twitter)へ投稿した統一教会への批判
『統一教会は、組織的な正体隠し勧誘から伝道目的を隠したまま一般市民を偽装教化施設に通わせ、思考の枠組みを変容させ信者を“生産”してきた。そんな反社会的団体からの脱会を望む家族と当該信者の話し合いを教団側が「拉致監禁!強制棄教だ!」と被害者面でアピールしているだけ。』
地裁判決が認容した問題箇所
2025年1月31日の地裁判決では原告の請求をほとんど棄却したが、訴因②と③について「引きこもり」が名誉棄損になるとして請求額の1%である11万円の支払いを命じた。
判決では②と③、2つの訴因にある「引きこもり」との記述や発言を名誉棄損としたが、2015年の時点で原告は何の抗議もしていない。私が有名になり、影響力が増した途端に統一教会への解散命令請求を止めようとして訴訟を起こしたのだ。「引きこもり」という言葉も自分の意思で留まっていた人という客観的な状態を示す言葉として用いたものだ。「引きこもり」は「様々な要因の結果として、就学や就労、交遊などの社会的参加を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭内にとどまり続けている状態を指す現象概念」である。
訴因③も、テレビ番組のコメンテーターとして出演した際に民事上の確定判決に対して論評をしたに過ぎない。だが、東京地裁はこの論評自体を名誉棄損とした。
原告は街頭で正体を隠して勧誘する偽装伝道を行う伝道機動隊として活動しており、心配した親族が脱会説得を試みた際にトラブルとなり「長期間監禁された」と訴え、民事訴訟で2015年に勝訴判決が確定している。一方、刑事事件としては不起訴となり、不服申し立てに対し検察審査会は「監禁されていたといえるか疑問である」として却下、不起訴相当との判断をしている。この検察審査会の決定などを総合的に判断して、当初の経緯はさて措き、原告が自分の意思で留まっていたものと思われることなどから、前記の通り論評した。何より問題なのは、民事訴訟判決への論評自体を名誉棄損としたことは表現の自由を侵害する惧れがあることだ。
一審の判決文には「裁判所の認定に批判を向けるものであれば格別」とあり、裁判所の判決への批判であれば問題ないような文言があるが、「判決の認定を覆すべき資料が存在していたと認めるに足りる証拠はない」として民事の判決内容に加えて新たな情報を得ていないのだから真実相当性がないとの判断をしており、やはり民事訴訟の確定判決への疑義や論評を認めていない。
この2点における一部敗訴について、高裁の判断を仰ぐため東京高裁へ控訴した。原告側も棄却された訴因に加え、訴因②で認定された記事の削除を求め控訴してきた。
これは表現の自由の観点からも問題であり、言論法(メディア・情報法)、ジャーナリズム、人権法(憲法)の研究を行う専門家であり、言論の自由、表現の自由についての日本の第一人者である専修大学の山田健太教授に意見書の作成を求めた。
控訴審で一審認容箇所を取消し
そして8月26日、東京高裁の佐々木宗啓裁判長は一審で認めた訴因②と③の判断を取消し、全面的に原告側の請求を棄却した。
判決では「引きこもり」について真実性を認めた上で、仮にそうでなくても真実相当性があったと認めている。そして別件民事訴訟の確定判決に対する論評(ミヤネ屋での発言)自体を名誉棄損とした1審判決を取り消した。一審判決で民事訴訟の確定判決への論評を名誉棄損と認定した箇所は以下の様に改められた。
『1審原告は、別訴高裁判決によって否定された事実は、これをもって本件各発言の真実性の証明として使えないことは明らかであるとした上で、1審被告は本件各発言は確定判決である別訴高裁判決に反した事実を。公然と適時して1審被国の名誉を毀損するものであるから、一審被告の真実性ないし真実相当性の主張は新規性のある証拠を持って行われるべきであり、そうでなければ一審被告は別訴高裁判決に経験則ないし最小法則に。関する明確な違法があることを論証しなければならない。などと主張する。しかしながら、民事訴訟は争訟当事者間の相対的紛争解決を図るためのものであり、原則として、その事件における手続き保障を与えられた当事者のみが裁判所の判断に拘束されるものであるところ、1審被告は別件訴訟の当事者ではなく、その他その訴訟手続に関与していた者でもないから、1審被告の本件訴訟における訴訟活動が別件訴訟における当事者の訴訟活動および別訴高裁判決の判断内容(なかんずく認定事実)に拘束されるべき理由はない。また、自由心証主義(民訴法247条)によれば、裁判所が、どの証拠からどのような事実を認定するか、認定した事実をどのように評価するかについて、過去に行われた裁判の事実認定またはその評価に拘束されることはないのであり、それは証拠が過去に行われた裁判のそれと事実上共通するような場合であっても変わるものではない。すなわち、本件訴訟において、別件高裁判決で認定されてない事実を1審被告が主張すること、さらに、裁判所がその事実を認定すること、別訴高裁判決で認定されている事実を1審被告が否定すること、さらに、裁判所がその事実を認定しないこと。いずれについても訴訟法上の制約がないことは明らかである』
この高裁判決によって確定判決への論評は担保され、表現の自由は守られた。一審の判断自体がおかしかったことは明白である以上、高裁判決はある意味で当然とも言えるが、この画期的判決を導いた山田健太教授の意見書を全文、以下に公開する。
画期的判決へと導いた山田健太教授の意見書を全文公開
意 見 書
本意見書は、判決を含む一連の訴訟に係る論評の自由について、法および判例上認められてきた取材・報道の自由を踏まえたうえで、表現活動としての判例批評を含む裁判を報ずるジャーナリズム活動の観点から意見を申し述べるものである。
1.ジャーナリズム活動に伴う表現行為は、より高度な表現の自由の保障の対象である
2.メディア環境の変容に伴い、一般人の読み方モデルの解釈は変わらざるをえない
3.裁判を報じ論評する自由は、民主主義社会の維持発展にとって重要な要素である